WX Briefing 実施上の基本的な考え方
・Briefingは相手を説得させる性質のものではない。
・情報の提供と相互の見方・意見交換の場であり、そこで両者の協議が行われる。
・気象状況を的確に判断し、簡潔・明瞭にまとめる。
・タイムリーな情報の提供が重要である。
・時間の管理を考えて行う。長過ぎても、短過ぎてもよくない。
・自分なりの結論(判断)を念頭におきながら、自信を持って行う。
・要領よく手短にポイントを絞って、声を大きくハッキリと説明すること。
(1)ウェザブリの準備
●地上天気図
①低気圧の位置と発達衰弱の度合い、その中心指度は
②高気圧の位置とその勢力範囲はどこまでか
③前線の位置とその影響範囲はどこまでか
④各地の天気概況と局地的な現象の有無(雷雨・視程障害現象・強風…)
●高層天気図
①850hPa面天気図
1)等温線の間隔は
2)湿域(T-Td<3℃)の分布状態は
3)高気圧・低気圧の位置は、地上天気図上のそれとどうか
4)風向きと風速は
②700hPa面天気図
1)湿域(T-Td<3℃)の分布状態は
2)高気圧・低気圧の位置は、地上天気図上のそれと比べてどうか
3)等高線の走行はどうか
4)風向きと風速は
③500hPa面天気図から
1)トラフ・リッジと地上天気図上の高気圧・低気圧との対応する位置関係は
2)高気圧・低気圧のいちは、地上天気図上のそれとどうか
3)等温線と等高線の走行は、また互いに交差しているか
4)風向きと風速は
5)等温線の間隔は混み合っているか
④300hPa面天気図から
1)ジェット気流の平面的な位置とその移動方向
●気象衛星画像
①広範囲な雲の出現分布域
②晴天域と曇天域又は悪天域との区別
③カラー写真の温度分布による雲頂高度の推定
④雲の分布域から、地上の低気圧・前線の位置の確認
●エマグラム
①大気の安定度は
②気温の逆転層、また逆転の種類は
③雲底高度は
④ウィンドシア―の有無、その高度と程度は
●雨雲レーダー合成図
①降水域の分布範囲
②地上低気圧・前線の位置の確認
③エコー頂から対応する雲のおおよその高さ
④エコーの強弱により、対応する雲の種類(強いエコーはCb)
⑤エコの―強弱から、降水現象の程度は
●TAF/METAR
●ピンポイント天気予報
B. 天気図等の色塗り
<目的>見やすく、分かりやすくすることによる見間違い等の防止、と一目瞭然。
①地上天気図
②高層天気図
| 850hPa | 700hPa | 500hPa | 300hPa | |
|---|---|---|---|---|
| 等温線 | 赤色 -6℃ラインは太線 (冬季) |
赤色 -12℃ラインは太線 (冬季) |
赤色 -30℃ラインは太線 (冬季) |
× |
| 湿域 T-Td < 3℃ |
緑色 | 緑色 | × | × |
| トラフ リッジ |
× | 太い実線 波形の実線 |
太い実線 波形の実線 |
太い実線 波形の実線 |
| H 高気圧 L 低気圧 |
青色 赤色 |
青色 赤色 |
青色 赤色 |
青色 赤色 |
| C 寒気 W 暖気 |
青色 赤色 |
青色 赤色 |
青色 赤色 |
青色 赤色 |
C. 天気図等の気象資料の提示
ブリーフィングしやすいように、数日前の天気図等を重ねて掲示しておく。
地上天気図の場合は、過去6時間前 又は 12時間前の天気図も並列に掲示する。
天気図等の隅に、やや大きな字で、日時を日本時間で書き示しておく。
(2)解析の実施
a. 現況はどうなのか?
b. 以前はどうであったか? …… 天気図の比較検討
c. 今後の予想はどうなるのか?
・今後、3時間後、6時間後はどうなるのか?
・VMCが今後とも続くのか?
・VMC → × はいつ頃か?
・ × → VMCはいつ頃か?
【予報の手順】
a. 過去の天気図と現在の天気図から、移動速度を、
高層天気図の等高線の走行からは、移動方向をそれぞれ割り出し、今後の推定位置を決定する。
b. 500hPa天気図上のトラフの動きを追跡し、今後の予想位置を決定する。
c. 渦度図及び鉛直流図の24時間予想図を利用する。
d. 気象衛星「ひまわり」画像を「動画」として、雲等の変化傾向を把握する。
e. 高層天気図(500hpa, 300hPa)から、ジェット気流の位置と強さを確認数する。
f. 悪天予想天気図の利用。
g. 気象通報から、TAF等をチェックしてみる。
※移動する前線の位置の特定法
① 風向・風速の変化に着目
② 顕著な気温差があるか
③ 降水域の広がりは
④ 気圧の値は
⑤ 寒冷前線の通過後の天気変化は
1)雲形……通過前までの層雲(Ns,St)から積雲(Cu)に変わる。
2)雨 ……地雨性からしゅう雨性に変わる。
※今後の前線の予想位置の推定法
外挿法
※天気は西から東に動く。
日本周辺の地名を知ろう!
① 高気圧・低気圧又は前線等の位置を説明する時に用いる。
② ボッ海と黄海及び東シナ海の区別は、ハッキリさせる。
③ 中国大陸は、北から、華北-華中-華南と大別される。
④ 日本列島は、北日本-東日本-西日本と3分割される。
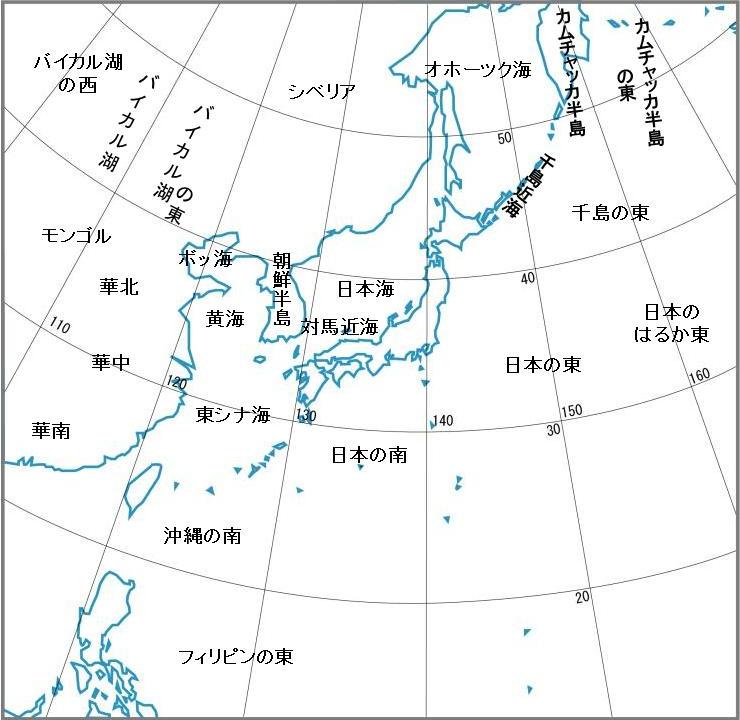
ブリーフィング用語等の使い分け
| 今日 | 夜明けから日没までの間(大体、午前6時から午後6時まで) |
|---|---|
| 今夜 | 日没から翌日の夜明けまで |
| 明日 | 翌朝の日出から24時間 |
| 朝のうち | 夜明けからおよそ午前9時頃まで |
| 昼過ぎ | 正午のあと2時間くらいまで |
| 夕方 | 日没の前後それぞれ1時間くらい |
| 宵のうち | 日没のあと2~3時間 |
| 夜半ごろ | 0時の前後それぞれ1時間くらい |
| ときどき | 日出から日没までの予報範囲の1/2未満の時間で、現象が断続的に数回起こる。 |
| 一時 | 現象が連続して起こり、予報範囲の1/4未満の時間。 |
| 日出 日没 | 太陽上辺が地平線(水平線)を出たとき、没したとき。 |
| 晴れ | SNOP通報式では、雲量2/8~6/8まで。10分雲量では、雲量8/10まで。 |
ブリーフィングの実施
本日使用します天気図は、
地上天気図につきましては、昨日の△△時と、本日◇◇時の、また、
高層天気図は、○日の□□時のものをそれぞれ使用します。
まず始めに、全般的な天気概況ですが、
地上天気図を見ますと、気圧配置や前線の推移ですが、
昨日と本日とを見比べますと、
高気圧、低気圧及び前線の移動は…………となっており、
現在の気圧配置の概略を説明し、実際の各地の天気変化はこうなっている。
この時に、今後の天気変化として、良くなりつつあるのか、悪くなりつつあるのか、
又は、あまり変わらないのかに重点をおいた説明をする。
次に、天気推移の理由付けとして、高層天気図の説明に入る。
高気圧・低気圧の位置、移動速度と方向、背の高さ、寒気・暖気の移流状態、発達、衰弱、
トラフ、リッジ、ジェット気流、高層風 等々の各項目を関連させて説明する。
その説明の補足資料として、
断熱図、合成レーダーエコー図、ひまわり雲解析図、その他を必要に応じて、適宜利用する。
一通りの説明が済んだら、
ローカル、又は、ルート訓練の地域に焦点を絞って、天気の予報について説明を進めていく。
この時、METAR/TAF 等を使用し、現在の訓練の終了予定時刻までの間の天気の予報を説明する。
以上でWX Briefingは終わります。